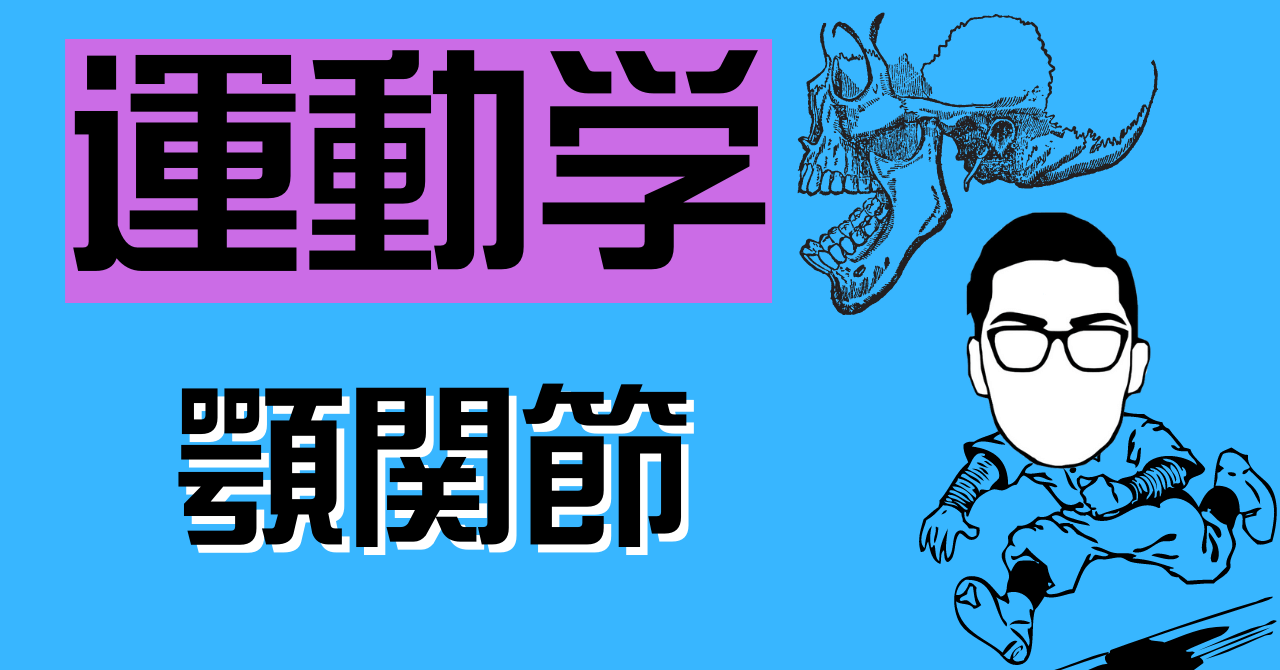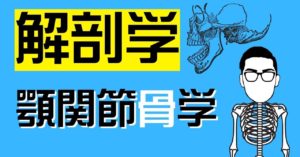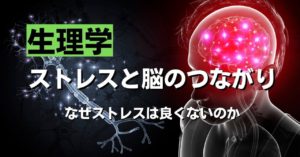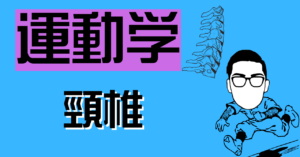どうも。スズキタケヒロです。
今回は顎関節の運動学です。
ここでは骨運動と関節内運動についてまとめていきます。
骨運動
下顎の運動は前方突出と後退、側方変位、下制と挙上です。
前方突出と後退
前方突出と後退は下顎が直線的に前後へ並進する動きになります。
したがって回旋などは含まれません。
前方突出と後退ができないと完全開口と閉口ができません。
側方変位
側方変位は側方への並進運動でその平均距離は成人で11mmが正常とされています。
側方変位は若干の回旋運動を伴い、歯科医は変位側をよく噛む側と評価するとかしないとか。
下制と挙上
開口運動は下制によって起こり、あくびなどが典型例で、成人では45〜50mm開くことが可能です。
だいたい3横指でPIPまで入ればそれくらいです。
食事などでは平均して18mmの開口が必要になり、2横指が入らない場合は異常とされます。
関節内運動
関節内運動は回転と並進の組み合わせで起こります。
回転運動は下顎頭と関節円板の下面の間で、並進運動は下顎頭と関節円板の両方が滑ることで起こります。
前方突出と後退
前方突出と後退の際、下顎頭と関節円板は一緒に下顎窩に対して前後へ並進します。
正常な成人では前後に1.25cmずつの移動が確認できるとされています。
側方変位
下顎窩の中で下顎頭と関節円板が側方へ並進する動きです。
側方変位最終域では変位側の下顎頭が視点になって非変位側の下顎頭が小さい円弧を描く動きをします。
下制と挙上
開口と閉口に最も関わる動きです。
これらの運動中は下顎頭、関節円板、下顎窩の間では回転と並進の組み合わさった動きが起こり、この並進運動を伴う回転運動は顎関節が全身中で最大になります。
この2つの運動が組み合わさることで噛む、すり潰すや会話などが可能になっています。
開口初期では可動域の30〜35%に達し、頭蓋に対して下顎が回転を起こし下顎体が後方へ動きます。
この回転が外側靭帯を緊張させ開口終期の開始の補助をしています。
開口終期では可動域の50〜65%に達し、回転運動から並進運動へと移行し、並進運動中は下顎頭と関節円板は前下方に向かって移動していきます。
完全開口時、関節円板は前方へ最大伸長され、これにより関節の適合性が向上しストレス軽減に役立っています。
閉口では開口で説明したのと逆の動きが起こります。
文章でダーっと説明してしまったのでイメージがしにくいかもしれませんが、そんな方はこちらをご覧ください。
このブログがあなたの臨床の一助になれば幸いです。
日々の臨床課題や悩みをディスカッション形式で解決。
ミーティングには様々な臨床家(柔整、鍼灸、カイロetc)が参加するので幅広い知見が手に入ります。
月に1〜2回メンバー限定のウェブセミナーも開催。
臨床力の向上を目的とした考え方や鑑別視点などを共有し、あなたのセラピストライフが充実。
施術アプローチや鑑別法、エクササイズや臨床知見などの動画・記事コンテンツも多数。
日々臨床の壁にぶち当たり、なかなか上手くいかなずに悩んでいるあなたへ。
今すぐ臨床課題を解決してみませんか?
申込時の会費が永年適用されます。
入会に際しての不明点などは遠慮なくお問い合わせください。
2021.11よりスズキタケヒロ公式LINEスタート
いろんな美味しい情報配信してます。(マジで
機運は行動した者にのみ訪れる。