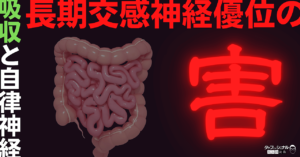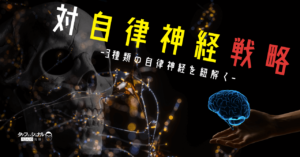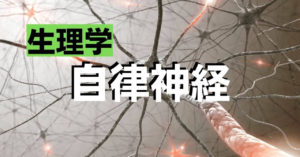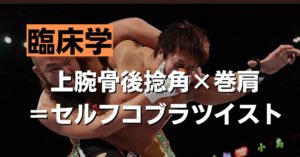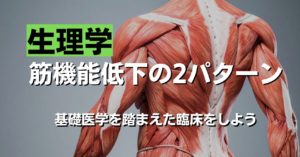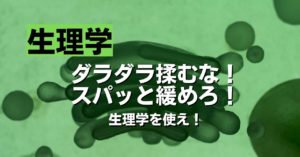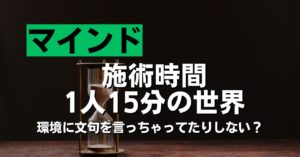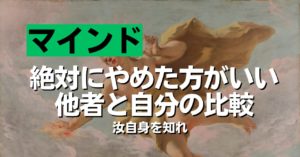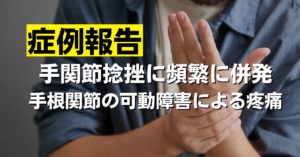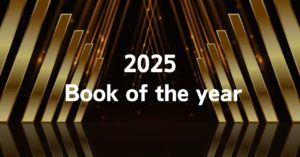どうもどうも
シリーズ:タケフェッショナル7弾です。
今回は~代謝と自律神経~長期交感神経優位の害についての内容になります。
しつこいですが。
短期間の、一時的な、循環的な交感神経優位は体にとって必要な機能なので交感神経優位=害ではないことにご注意ください。
害なのは長期の交感神経優位ですからね。
この記事は単体で読んでもほぼ理解不能な可能性が高いのでご注意ください。
「長期交感神経の害」シリーズというものがあり
まずはこれ↑を読み
次にこれ↑を読むことで話が繋がります。
ここで問題です。
自律神経は全部で何種類でしょう?
正解は…
2種類
ではありません。
2種類と答えた方は悪いことは言わないのでこの記事から読んでください。
そもそも「長期交感神経の害」シリーズを読む前に、自律神経を解ってない人はこの記事を読まないと何のこっちゃになる可能性すらあります。
とは言え何を読むかは個人の自由です。
が
ぼくは忠告はしましたからね。
この記事だけを読んでおきなら「読んでも意味わからん!」はなしでお願いしますね。
1.自律神経による血流パラドクス
もしかしてもしかするとチェックしてない人もいるかもしれないのでいつもの内容は置いておきます。
1-1.交感神経優位になると
交感神経優位になると骨格筋と脳への血流が優先されます。
これが長期間続くと内臓への血流が不足し始めます。
この血流不足の情報は迷走神経を介して脳へ伝わります。
ここで脳はバグり始めます。
交感神経の作用で骨格筋への血流分配の命令パルスを出しながら、辺縁系(本能)の部分では内臓への血流分配を命令しています。
こうなるとやはり本能の方が強く、結果的に骨格筋は低血流(低酸素)状態での活動を強いられます。
そして筋内に乳酸が蓄積し、疲労やコリといった現象が起こります。
果たして疲労やコリが揉んで良くなるのかどうか疑問ですね。
リラクゼーション効果により副交感神経が立ち上がってくれれば効果あるのかもしれませんが。
1-2.長期ストレスではどうなるか
ストレスと脳の関係はこのブログで確認願います。
解ってるテイで話が進めますのでご注意ください。
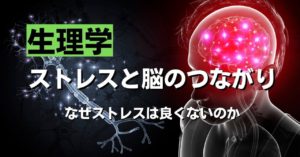
ようは交感神経のストッパーと副交感神経のブースターが機能しなくなるって話でしたよね。
じゃあストレスって何?ってなると多種多様な回答になりますよね。
人によって違いすぎるので。
仕事、人間関係、お金、離婚、破局など色々ありますね。
2.代謝とのつながり
ここでは自律神経と肝臓のつながりを考えます。
ちなみに
「心臓、肺(=呼吸)」ならこの記事
・自律神経とは?
・なぜ自律神経がエラーを起こすのか?
・エラーを起こすとどうなるのか?
・どうやってエラーを改善していくのか?
そんな内容が書かれています。
「食道、胃、十二指腸(=消化)」ならこの記事
・消化とは?
・なぜ消化にとって自律神経のエラーが良くないのか?
・自律神経エラーが起こると消化がどうなるのか?
・自律神経エラーが起こると胃・十二指腸の細胞はどうなるのか?
そんな内容が書いてあります。
「小腸・大腸(=吸収)」ならこの記事
・吸収とは?
・なぜ吸収にとって自律神経のエラーが良くないのか?
・自律神経エラーが起こると吸収がどうなるのか?
・そもそも消化がダメになると吸収はどうなるのか?
・自律神経エラーが起こると小腸・大腸の細胞はどうなるのか?
そんな内容が書いてあります。
この記事では上記3つの内容が解っているテイで話が進みますのご注意ください。(2回目)
2-1.そもそも代謝とは?
代謝ってなんですか?と聞かれて説明できる人はこの項はすっ飛ばしてください。
そうではない人は次の絵を見てもらえればすぐに理解できると思います。